◆【映画】『ぼくが生きてる、ふたつの世界』の作品情報
- 監督:呉美保
- 脚本:港岳彦
- 原作:五十嵐大
- 出演:吉澤亮、忍足亜希子、今井彰人、烏丸せつこ、でんでん 他
- 配給:ギャガ
- 公開:2024年
- 上映時間:105分
- 製作国:日本
- ジャンル:ヒューマンドラマ、家族ドラマ
- 視聴ツール:Netflix、自室モニター、Anker Soundcore AeroClip
◆キャスト
- 五十嵐 大:吉沢亮 代表作『キングダム』(2019)
- 五十嵐 千草(母):忍足亜希子 代表作『ゆずり葉』(2009)
- 五十嵐 忠(父):今井彰人 代表作『LISTEN リッスン』(2016)
- 編集長:ユースケ・サンタマリア 代表作『踊る大捜査線 THE MOVIE』(1998)
- 祖母:烏丸せつこ 代表作『青春の殺人者』(1976)
◆ネタバレあらすじ
宮城県の小さな港町で育った五十嵐大は、耳のきこえない両親のもとで、愛情いっぱいに育てられます。幼い頃の大にとって、母の“通訳”をすることは特別なことではなく、当たり前の日常でした。しかし成長するにつれて、「きこえない親を持つ子」として周囲から向けられる特別な視線に戸惑い、次第に苛立ちを募らせていきます。明るく前向きな母の姿さえ重く感じるようになった大は、家族にも自分にも居場所を見いだせません。やがて20歳になった彼は、すべてから逃れるように上京し、誰も自分の背景を知らない東京でアルバイトをしながら暮らし始めます。きこえる世界ときこえない世界、その二つのあいだで揺れる大が、自分自身の人生と家族への思いにどう向き合っていくのかが描かれていきます。
ここからネタバレありです。
ネタバレあらすじ(クリックで開閉)
大の物語は、生まれた直後から始まります。耳のきこえない父・陽介と母・明子に囲まれ、幼い大は手話と声を自然に行き来しながら育ちます。母に字を教わり、自分で書いた手紙を家のポストに入れてやりとりする幼少期の時間は、後に彼が「言葉を書く人」になる原点となっていきます。
しかし、小学校に上がると状況が変わります。友達が家に来たときのよそよそしい視線、近所の大人たちが向ける「特別な家庭を見る目」に、大は次第に息苦しさを覚えます。中学に入るころには反抗期が強まり、「自分の家族のせいで普通に生きられない」と感じるようになり、高校受験に失敗した苛立ちも重なって、母に「こんな家に生まれたくなかった」と激しい言葉をぶつけてしまいます。
それでも両親は大を責めず、祖父の強引さもあって、大は東京の編集プロダクションで働くチャンスをつかみます。ユースケ・サンタマリア演じる編集長のもとで雑用から始め、やがて記事を書く仕事を任されるようになるなかで、大は再び手話を使うろう者たちと出会い、自分とは違う形で「きこえない世界」を生きる人たちを見つめ直していきます。彼らとの交流を通じて、かつて息苦しさの原因だと思っていた両親の人生にも、別の光が差し込み始めます。
ある日、父の倒れた知らせを受け、約8年ぶりに故郷へ帰る大。そこで彼は、昔と変わらない母のまなざしと、自分が投げつけた言葉をなお受け止めてくれている家族の姿に向き合うことになります。再び東京へ戻る日の見送りの場面で、母は若い頃と同じように、街中でも臆することなく手話で大に想いを伝えます。その無音のやりとりの中で、大は上京前に一緒に背広を選んでくれた日のこと、手紙をやりとりした幼い日の記憶を重ね合わせ、自分がどれほど多くの愛を受け取っていたかをようやく理解し、涙があふれます。
東京へ向かう列車がトンネルを抜けるラスト、大は自分の半生と家族の物語を言葉として書き残そうと決意します。きこえる世界ときこえない世界、そのどちらか一方ではなく「ふたつの世界」を生きてきた自分の人生を受け入れる、その静かな覚悟の瞬間で物語は幕を閉じます。
◆考察と感想
俺の考察&感想
『ぼくが生きてる、ふたつの世界』は、特別な出来事を派手に描く作品ではないのに、観たあと静かに胸の奥が締めつけられるような重さと、じんわりと温かくなる余韻を残す映画だった。特に、耳のきこえない両親と、きこえる息子である大が抱える“目に見えない距離”が、あまりにもリアルで、時に痛いほどだった。家族はどれだけ愛していても、理解しきれない部分を抱えているものだし、この映画はその“どうしようもないズレ”から逃げず、丁寧に描き切っていたと思う。
大が幼い頃、母の通訳をする姿に違和感がないのは、彼にとってそれが当たり前の生活だからだ。彼はただ母を助けたいだけで、そこに特別な意味なんてない。ところが、少しずつ他者の視線を知っていく。友達が家に来た時の微妙な空気、近所の大人たちが向ける好奇や偏見、そういった“外側の世界”が、大の中に「もしかしたら自分の家は“普通”じゃないのか」という疑念を生む。これは誰にでも覚えがある感覚だと思う。幼い頃は家が世界のすべてだったのに、成長するほど、自分の家だけが妙に浮いて見えたり、恥ずかしく思えたりする時期がある。それがたまたま大の場合は「親がろう者である」という事実に結びついただけで、根本的には普遍的な“思春期の痛み”に近い。

宮城県の小さな港町。愛情いっぱい与えられた大だったが、コーダとして“親の通訳”という役割も背負っていく。
だからこそ、中学生になった大の荒れ方にはものすごく説得力があった。「こんな家に生まれたくなかった」と母に吐き捨てるシーン。あれは生々しくて、観ていて胸が痛んだ。どれだけ愛されていても、親の存在が重いと感じる時期があるし、大の苛立ちの方向がたまたま母に向いてしまっただけだ。だが、母は怒らず、悲しみも見せず、ただ息子を受け止める。その忍足亜希子の表情が圧巻で、大の痛みも母の痛みも、同時に胸を刺してきた。
映画の前半は大がしんどい時間をひたすら蓄積し、息苦しさを観客にも共有させるような構造になっている。だが、その息苦しさがあってこそ、後半の東京編が効いてくる。大が地元を離れ、「誰も自分の背景を知らない場所」に身を置くことで初めて、自分がどれだけ両親に支えられてきたかを“距離を介して”理解していく。その過程が本当に自然でうまい。耳のきこえない人たちとの出会いで、大は初めて“きこえない世界”を客観視することができる。親とは違う生き方をする彼らと触れることで、親の人生もまた一つの選択であり、苦労だけでなく喜びもあるということに気づいていく。これがとても大事で、視野が狭い時には“家族の事情=自分を苦しめる原因”としか見えなかったものが、離れることによって別の角度から見られるようになる。これは多くの人間が成長の中で経験する感覚だと思う。

父・陽介が倒れたと聞き、病院に駆け付ける吉澤亮演じる大。家族から距離を置いた彼が、再び故郷と向き合う転機となる場面だ。
そして物語のクライマックスにあるのが、母との「静かな再会」だ。大人になって帰省した大が、上京前の出来事を思い出しながら母と向き合う場面。街中で躊躇なく手話を使い、大に想いを伝えようとする母。その手話が大にとっては“痛み”だったはずなのに、この瞬間は“愛の形”として受け入れられる。ここで初めて、大は母の視線と真正面から向き合うことになる。母はずっと変わらず想い続けていたのに、大だけがその重さに気づけていなかった。吉沢亮の泣き顔の演技がとにかく見事で、気づいた瞬間の崩れ方がリアルすぎて胸を打った。
最終的に、大は「ふたつの世界」を経験したからこそ、自分の言葉で表現しようと決意する。幼少期に手紙を書いたことが、ここで“書くという行為”の原点として回収される構成がすごく美しい。そしてラストの、東京へ向かう列車がトンネルを抜けるカット。これは「過去の暗がりから抜け出し、光へ向かっていく」象徴であり、大の人生がようやく自分の足で進み始めたことを示す最高の締め方だった。派手さはないが、人生の痛みと愛を誠実に描いた傑作だった。
モテ男の考察&感想
家族との距離感に悩む大の姿は、恋愛でもよくある“自分の弱さを誰にも見せられない男”そのものだ。だからこそ、大が母の愛を受け止められた瞬間は、男としての殻が破れたタイミングでもある。自分の弱さを認められる男は、他人の感情もきちんと受け止められる。つまり“大の成長”は、そのまま“魅力ある男になるプロセス”でもある。家族を理解できる男は、恋人の心も理解できる。そう思わせてくれる物語だった。
◆教訓・学び
弱さや本音を隠さず向き合える男こそ、ふたつの世界を理解し、人の心を深くつかむ。
ただのレビューで終わらせない。“男前にビシッと決める”映画知識を身につける場——シネマログ。
会話で効くネタ、俳優・ジャンルの基礎教養、デートで外さない選び方までを要点だけ端的に。
◆似ているテイストの作品
- 『ひとよ』(2019年/日本)
家族の間に積み重なってきた“言えなかった本音”や、親と子の複雑な距離感を丁寧に描く点が本作と深く共鳴します。
それぞれが抱える痛みと不器用な再生を静かに紡ぐ空気感は、『ぼくが生きてる、ふたつの世界』が好きな人に刺さるドラマです。 - 『ファミリア』(2023年/日本)
“家族とは何か”という普遍的なテーマを、異なる価値観・文化を持つ人々の交流を通して描く構造が非常に似ています。
血縁や境遇を超えて「家族の形」を問い直す物語で、静かな感動と人間ドラマの奥行きが本作と強く響き合います。
◆評価
| 項目 | 点数 | コメント |
|---|---|---|
| ストーリー | 18 / 20 | CODAとして生きる主人公の葛藤と、親子が“離れて気づく愛”を丹念に積み上げた物語が秀逸。静かな展開の中に揺らぎと痛みがあり、人生の瞬間瞬間が丁寧に描かれている。 |
| 演技 | 18 / 20 | 吉沢亮の繊細かつ荒れた内面表現が圧巻。特に泣き崩れる場面の説得力は突出している。忍足亜希子の“ごく普通の母”としての佇まいも胸を突き、キャスティングの妙が光る。 |
| 映像・演出 | 18 / 20 | 呉美保監督ならではの生活の質感、静かな時間の積み重ねが美しい。海辺の町と東京の対比、手話の“音のない会話”を映像で魅せる演出が深い余韻を生む。 |
| 感情の揺さぶり | 18 / 20 | 母を疎ましく思う時期、距離を置いて初めて見える愛、そして再会の静かな涙。派手な盛り上げに頼らずとも、積み重ねた感情が一気に溢れるクライマックスは強烈だった。 |
| オリジナリティ・テーマ性 | 19 / 20 | “きこえる子ときこえない親”というテーマを特別扱いせず、どの家庭にもある普遍的な距離感として描いた点が見事。実話ベースながら映画的構成としても非常に完成度が高い。 |
| 合計 | 96 / 100 | 静かで力強い家族ドラマ。痛みを抱えた青年が“ふたつの世界”を生きる中で、ようやく愛の形を掴み直す姿が胸を打つ。呉美保監督らしい温度と余白をまとった傑作。 |
※本レビューの点数は、シネマログ独自の
映画評価基準(5項目・100点満点)
に基づいています。
◆総括
『ぼくが生きてる、ふたつの世界』は、特別な題材を扱いながら、それを“特別な物語”として語らないところにこそ価値がある作品だったと思う。ろう者の両親と、きこえる息子という環境は確かに特殊だが、そこで描かれる「家族への苛立ち」「距離を置いて初めて気づく親の愛」「自分の居場所を探す痛み」は、誰にとっても身に覚えのある普遍的なテーマだ。だからこそ、大の成長を追う時間がそのまま観る側の記憶を揺らし、胸の奥の柔らかい部分に触れてくる。
呉美保監督の静かな演出が、この物語に圧倒的な説得力を与えている。派手な演出や劇的な展開に頼らず、日常の手触りや言葉にならない瞬間を丁寧に積み重ねることで、家族の愛も痛みも、息苦しさも温もりも、ひとつひとつが鮮やかに立ち上がる。特に母と大の「無音の会話」を描くシーンは、音がないのに心の奥が震えるほど雄弁だった。
そして、大が“ふたつの世界”をただ行き来するのではなく、最終的にそれを“自分のものとして受け入れる”ところにこの映画の核心がある。誰にでも逃げたい過去、見たくない部分はある。だが、それを抱えたままでも前に進めるのだと、大の姿が静かに教えてくれる。本作は、特別な家族の話ではなく、「家族と自分をどう向き合っていくか」という誰もが通る問いに、深い余白と温もりをもって答えてくれる作品だった。静かで、優しくて、痛みがある。そして確かな希望がある。そんな余韻がずっと残り続ける、心を揺らす一本だった。
🎧 最近ほぼ毎日使っているコスパ最高のワイヤレスイヤホン
最近はほぼこのワイヤレスイヤホンを使っている。軽い・痛くない・外で落ちないの三拍子が揃っていて、コスパが良すぎる。
Anker Soundcore AeroClip(Bluetooth 5.4)
【オープンイヤー型 / イヤーカフ型 / IP55防塵・防水 / 最大32時間再生 / マルチポイント対応】



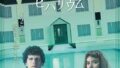
コメント